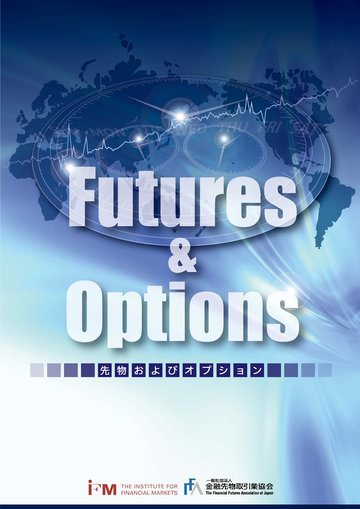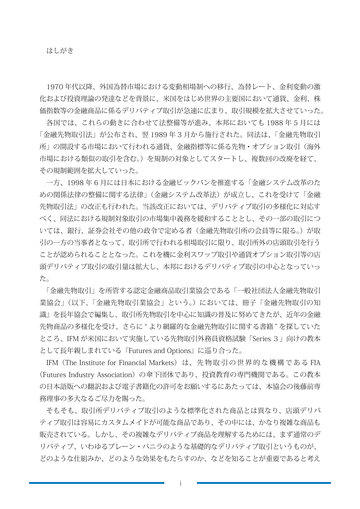Futures&Options
Futures&Options
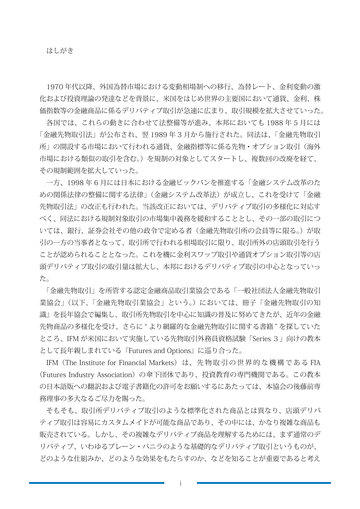
- ページ: h1
- はしがき
1970 年代以降、外国為替市場における変動相場制への移行、為替レート、金利変動の激 化および投資理論の発達などを背景に、米国をはじめ世界の主要国において通貨、金利、株 価指数等の金融商品に係るデリバティブ取引が急速に広まり、取引規模を拡大させていった。 各国では、これらの動きに合わせて法整備等が進み、本邦においても 1988 年 5 月には 「金融先物取引法」が公布され、翌 1989 年 3 月から施行された。同法は、 「金融先物取引 所」の開設する市場において行われる通貨、金融指標等に係る先物・オプション取引(海外 市場における類似の取引を含む。 )を規制の対象としてスタートし、複数回の改廃を経て、 その規制範囲を拡大していった。 一方、1998 年 6 月には日本における金融ビックバンを推進する「金融システム改革のた めの関係法律の整備に関する法律」 (金融システム改革法)が成立し、これを受けて「金融 先物取引法」の改正も行われた。当該改正においては、デリバティブ取引の多様化に対応す べく、同法における規制対象取引の市場集中義務を緩和することとし、その一部の取引につ いては、銀行、証券会社その他の政令で定める者(金融先物取引所の会員等に限る。 )が取 引の一方の当事者となって、取引所で行われる相場取引に限り、取引所外の店頭取引を行う ことが認められることとなった。これを機に金利スワップ取引や通貨オプション取引等の店 頭デリバティブ取引の取引量は拡大し、本邦におけるデリバティブ取引の中心となっていっ た。 「金融先物取引」を所管する認定金融商品取引業協会である「一般社団法人金融先物取引 業協会」 (以下、 「金融先物取引業協会」という。 )においては、冊子『金融先物取引の知 識』を長年協会で編集し、取引所先物取引を中心に知識の普及に努めてきたが、近年の金融 先物商品の多様化を受け、さらに “ より網羅的な金融先物取引に関する書籍 ” を探していた ところ、IFM が米国において実施している先物取引外務員資格試験「Series 3」向けの教本 として長年親しまれている『Futures and Options』に巡り合った。 IFM(The Institute for Financial Markets) は、 先 物 取 引 の 世 界 的 な 機 構 で あ る FIA (Futures Industry Association)の傘下団体であり、投資教育の専門機関である。この教本 の日本語版への翻訳および電子書籍化の許可をお願いするにあたっては、本協会の後藤前専 務理事の多大なるご尽力を賜った。 そもそも、取引所デリバティブ取引のような標準化された商品とは異なり、店頭デリバ ティブ取引は容易にカスタムメイドが可能な商品であり、その中には、かなり複雑な商品も 販売されている。しかし、その複雑なデリバティブ商品を理解するためには、まず通常のデ リバティブ、いわゆるプレーン・バニラのような基礎的なデリバティブ取引というものが、 どのような仕組みか、どのような効果をもたらすのか、などを知ることが重要であると考え i
�
- ▲TOP
 Futures&Options
Futures&Options Futures&Options
Futures&Options